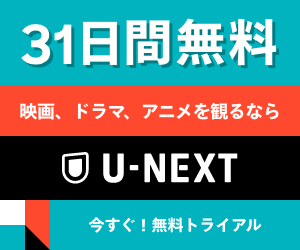映画『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』は、イラク戦争の大義名分と言われる「大量破壊兵器」を理由としたイラクへの侵攻を阻止すべく、アメリカ政府による歴史的な陰謀に立ち向かい、不屈の精神で”真実”を伝え続けた新聞紙者たちの実話を描いたノンフィクション社会派ドラマです。
「スタンド・バイ・ミー」「恋人たちの予感」「最高の人生の見つけ方」など多くのヒット作を生んだハリウッドの巨匠ロブ・ライナー監督が、2003年イラク戦争開戦時から15年間温め続けたという構想を作品にしたもので、監督・制作のみならず、ロブ・ライナー監督自らも支局長役を演じています。
「大量破壊兵器」の存在に疑問を抱き真実を追いながら、戦い続けた実在の記者たち4人の奮闘を描いた『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』。イラン戦争が始まった当時は、”NHKの記者”をしていたジャーナリストの池上彰さんが、字幕監修をしていることでも話題となりました。
今回は、映画『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』を観た感想や解説、撮影秘話や考察を書いていきます!
目次
映画「記者たち~衝撃と畏怖の真実~」を観て学んだ事・感じた事
・イラク戦争開戦の裏側で起きていた”記者たちの戦い”を知ることができる
・純粋に真実を伝えることがジャーナリズムの命
・人間の愚かさへの皮肉と反戦メッセージが込められた社会派映画
映画「記者たち~衝撃と畏怖の真実~」の作品情報
| 公開日 | 2018年7月13日(アメリカ) 2019年3月29日(日本) |
| 監督 | ロブ・ライナー |
| 脚本 | ロブ・ライナー マシュー・ジョージ エリザベス・E・ベル |
| 出演者 | ジョナサン・ランデイ(ウディ・ハレルソン) ウォーレン・ストローベル(ジェームズ・マースデン) ジョー・ギャロウェイ(トミー・リー・ジョーンズ) ヴラトカ(ミラ・ジョヴォヴィッチ) リサ(ジェシカ・ビール) ジョン・ウォルコット(ロブ・ライナー) |
映画「記者たち~衝撃と畏怖の真実~」のあらすじ・内容

2001年9月11日のアメリカ同時多発テロをきっかけに、当時のアメリカ大統領ジョージ・W・ブッシュは国連総会の演説でテロとの戦いを宣言し、イスラム系テロ組織アルカイダの指導者であるオサマ・ビンラディンを首謀者と断定します。
そんな中、地方新聞社など31紙の新聞社を傘下に持つナイト・リッダー記事配信社のワシントンD.C.支局長であるジョン・ウォルコットは、ブッシュ大統領がビンラディンだけでなくイラクのサダム・フセイン大統領との戦争も視野に入れているという情報を得ます。
ウォルコットはその真相を掴むべく、部下であるジョナサン・ランデーとウォーレン・ストロベルに調査取材を命じます。
2人による地道な裏付け取材の末、ウォルコットはアメリカ政府がビンラディンとフセインが裏で繋がっているという確固たる根拠もなしに、イラクへの軍事介入を進めていることを突き止めます。
しかし、記者たちの奮励もむなしく、2002年1月29日に行われた一般教書演説でブッシュ大統領がイラクを非難する「悪の枢軸発言」を行います。これを皮切りに、アメリカの大手新聞社ニューヨークタイムズ、ワシントン・ポストなどをはじめ、CBSやABC、FOXといった有名メディアまでもがアメリカ政府の方針に軒並み迎合。
その結果、根拠のない政府の情報を前提に世間に報道したがために、一般世論の行き過ぎた愛国主義に拍車をかけてしまいます。
それでも、政府による隠ぺいやねつ造、情報操作などの”嘘”を追及する姿勢を崩さないナイト・リッダー社は、ベトナム戦争時の元従軍記者であったジャーナリストのジョー・ギャロウェイを招請し、ジャーナリズムの信念のもと真実を世に知らしめるべく、イラク戦争開戦のXデーまで必死に動き続けるのでした。
映画「記者たち~衝撃と畏怖の真実~」のネタバレ感想
印刷物として世に出なかった真実の実話
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.「イラクには大量破壊兵器はなかった」という事実は、今となっては周知の事実ですが、同時多発テロ直後の当時の人たちにとっては、とても信じがたい話だったと思います。
現に、当時はアメリカをはじめ世界中の人々がテロの参謀者と言われるビンラディン氏の行方や、イラクが所持していたとされる大量破壊兵器の存在に注目していましたよね。
イラク大統領サダム・フセインがテロ組織の後ろ盾をしているという疑惑が国際社会で膨らみ開戦に至るなか、ナイト・リッダー社だけが真実を追い続けジャーナリズムの信念を貫きました。
当時の人たちにとっても、ベトナム戦勝と同じ轍を踏まぬよう身を粉にして動いていた記者たちがいることを知る人はほとんどいなかったでしょうし、知っていたとしても耳を傾ける人は少なかったということがこの作品でも描かれています。
アメリカ政府による陰謀の詳細、それを裏取りする記者たちがいること、真実を追い求めるにつれ身の危険を案じて怯える記者の家族たち、戦争を止めたいという思いから取材を受ける決意する政府関係者、曲げられた事実を信じて自ら入隊志願する青年兵…
登場人物たちや劇中に出てくる数字の数々によって、さまざまな角度から切り取られた同時多発テロからイラク戦争開戦までの舞台裏。これは決して語られることがなかった真実の物語と言えますし、映画を観ていても色々な感情が溢れてきます。
アメリカ政府によってガチガチに固められた嘘を暴こうと奮闘する新聞記者たちの勇猛心やジャーナリズムに込められた熱意、開戦反対を願い勇気を出して告発する政府関係者の気持ちを思うと、結末が分かっていても応援したくなりました。
また、世界に向けて平気で嘘をつき戦争を始めてしまうアメリカ政府に対しては、恐怖すら覚えましたし、嘘の内容や陰謀のキーパーソンが名指しで出てくるあたりはさすがアメリカの映画だなとも感じます。
当時の様子を蘇らせる映像フッテージの数々
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.2001年9月11日に起きたアルカイダによるアメリカ同時多発テロ。世界中が衝撃を受けた世界貿易センタービルが崩壊していく衝撃的な映像、ブッシュ大統領による開戦宣言の歴史的瞬間や世界中での反戦デモの様子などは、当時の日本でも報道されていたので覚えているという人は多いのではないでしょうか?
ドキュメンタリー映画のように所々に重ね合わされたフッテージフィルムの数々は、時代を超えて観ている側の目に今までとは違った印象を与えます。
この映像フッテージによる演出、映画としては特別珍しい演出ではありませんが、記憶に新しい過去の実話を題材にしているからこそ、今までとは違った形で楽しめる要素でもあります。
同時多発テロやブッシュ大統領の演説などの記憶があまりない世代にとっても、このフッテージを見せられることでよりリアリティを感じ、物語の表舞台とその裏側、真実と嘘のギャップを感じれるのではないでしょうか。
作品のサイドストーリーでもある黒人青年が、ツインタワーが崩壊していくさまを目撃し、19歳という若さでアメリカ兵として志願する様子も、同じ世代の人が鑑賞することでより自分と重ね合わせ安くなっている点からも、当時を知らない人はドキュメンタリーとして観てみるのもいいかもしれませんね。
監督の”15年プロジェクト”のもと集結した豪華キャスト
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.4人の少年たちのひと夏の冒険を描いた「スタンドバイミー」や、観た人にトラウマを与えるようなホラー映画「ミザリー」など、数々のジャンルで映画を作り上げてきたロブ・ライナー監督。
今作品はイラク戦争開戦当時から映画化を決意しその構成をあたため続けていた、まさに”15年プロジェクト”だったそうで、声をかけたキャストたちもすぐさま返事をしてくれたとインタビューで語っていました。
主役、脇役を問わず幅広いジャンルで出演し日本でもお馴染みの俳優トミー・リー・ジョーンズをはじめ、悪役やスキャンダラスな役を得意とするウディ・ハレルソン、ルックスだけでなく、演技でも評価の高いジェームズ・マースデン、バイオハザードシリーズでもお馴染みのミラ・ジョヴォヴィッチなど豪華なキャストが見どころでもあります。
そして、監督だけでなく役者としても出演しているロブ・ライナー監督、実は支局長役を依頼していたアレック・ボールドウィンが降板になって回ってきた役ということですが、ユーモラスで責任感ある頼れる上司ジョン・ウォルコット支局長を見事に演じていました。
ウォルコット支局長も4人の記者たちのうちの1人なので、この作品では主役級の役どころですが、監督業と俳優業の経歴を持ったロブ・ライナー監督だからこその妥協のないキャスティングと見事な演技をこなすことができたのではないでしょうか。
しかしこのウォルコット支局長、かなり良い人という役どころなので”監督自ら美味しいとこ取り”な配役には賛否両論ありそうですが、個人的にはロブ・ライナー監督の楽屋落ちが楽しめて面白かったですね。
また、どの作品に出てもひときわ存在感が大きいトミー・リー・ジョーンズらしい演技、その一方で存在感を消すほどに作品に上手く溶け込んでいるミラ・ジョヴォヴィッチにも、注目してみると面白いかもしれません。
【トリビア】リアリティを追及した本人指導の再現演技に脱帽!
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.この作品の中心人物でもあるジョナサン・ランデイ、ウォーレン・ストローベル、ジョー・ギャロウェイ、ジョン・ウォルコットら自らも撮影期間は殆ど現場に足を運び、自分を演じる役者それぞれに役作りや演技のアドバイスをしていたそう撮影秘話があります。
そのため、劇中でのジョナサンとウォーレンのコンビネーションや取材風景、通信社での仕事風景は本物のジャーナリストそのものとして再現されているようです。
もちろん、ノンフィクションといえ脚本はあるのでセリフやシーンにはある程度脚色はあるかもしれませんが、同時多発テロが起こった当日に車が使えずヘルメット姿にサイクリングスーツを着て自転車で出勤をするシーンや、告発を決意した政府関係者へインタビューをするシリアスなシーンは、本物のジャーナリストの仕事ぶりを観ている感覚になりましたね。
【トリビア】忠実に再現されたセットと支局長の名演説
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.劇中にでてくるナイト・リッダー社、残念ながら現在は無くなってしまった通信社なので、実際のオフィスでの撮影は出来なかったようですが、THE TIMES PICAYUNE BULIDINGという実在する新聞社がオフィスとして構えている建物の一部を借りて使用し、大掛かりなセットを作り忠実に再現したそうです。
また、ラストスパートを印象付けるウォルコット支局長が部下達を激励する名スピーチ。こちらも本来なら脚本家によるセリフが用意されていたそうですが、現場での判断によってジョン・ウォルコット氏本人のセリフを採用し、抑揚や強調した部分まで見事に本人を再現しているそうなのです。
「我々は人の子を戦地に送るヤツの味方ではない。わが子を戦地に送る者たちの味方だ」
ウォルコット支局長が実際に発した名演説が、当時を再現するセットの中で行われることで映画のワンシーンという垣根を越えて歴史の瞬間を切り取っている、そんな印象を受けるあの名シーンに胸が熱くなったのはた私だけではないはず。
【解説】当時の記者であった池上彰による字幕監修への思い
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.この作品で字幕監修をした池上彰もまた、当時はNHKの現役記者だったわけですが、彼自身もジャーナリストとしての作品への共感や思い入れは強かったのではないでしょうか。どこまで字幕付けに携わったのかは分かりませんが、米国記者同士が使っている”業界用語”を上手に拾い集めている印象でした。
英語のリスニングができる人なら気付いた人もいるかもしれませんが、ウディ・ハレルソン演じるジョナサンとジェームズ・マースデンが演じるウォーレンの記者コンビのやり取りや、政府関係者である取材相手との会話にも所々暗号のような単語が飛び交います。
劇中で1番分かりやすいシーンで例えるなら「誰が言った?」との返答に「五角形」と答えるシーンですが、「五角形」の形をしている建物はペンタゴン、つまりアメリカ国防総省の隠語になるといったものです。
そこで日本語字幕の漢字部分を「国防総省」にし、ルビを「ペンタゴン」と当てるなど、業界用語を見事に表現するのですが、その独特な記者たちの”英語版業界用語”を上手く日本語字幕に落とし込み表現しています。
この池上彰による、より正確に真実を伝えるための心配りともいえる日本語字幕や、裏方として鑑賞している側に政治情勢が分かりやすいようルビを上手く活用して解説する辺りは、さすがジャーナリストだなと感心する場面が多々あります。
ペンタゴンの名称は日本でもなじみ深いのでリスニングが苦手な人でも分かりやすいと思いますし、英語ができる人は意識して”記者たちの隠語”を見つけることで、より一層ジャーナリストたちの現場の臨場感を体験することができますよ!
【考察】眠くなる?ドキュメンタリー?”ノーエンターテイメント”にした監督の意図
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.実はこの作品、映画としてのエンターテイメント性は全くと言っていい程ないので、観る人によっても評価が分かれるところではありますね。劇中ではアクション要素もなければ感動要素もないですし、雰囲気づくりに使われるようなインスト音楽すらほとんど使われていません。
ストーリーも淡々と進んでいき、最終的には悪を負かすようなどんでん返しもないため「特番のドキュメンタリーを観ているみたい」「途中で眠くなってしまった」という感想を持つ人もいるのではないでしょうか。
しかし、敢えてノーエンターテイメントの映画にしたのは、ロブ・ライナー監督の意図があったのではないか?と私は考えています。
監督や制作スタッフが最もフォーカスを当てたかったのは「真実」。作品をつくる上でも「真実を伝えること」そして「正確に撮ること」にこだわり、不必要な演出は省いて淡々としたシーンの切り替えや構成をしたのではないでしょうか?
そのおかげで映画としてのエンターテイメント性は欠けたかもしれませんが、中立的な立場から鑑賞者へ事実を伝えることができ、映画自体が本来あるべきジャーナリズムの精神性で作られているような気がしました。
それと同時に「この映画を観ただけで情報を鵜呑みにしてはいけない」という監督からの警告も発信している気もします。
これをエンタメ映画として観たというひとつの面からすると、鑑賞者にとってあまり楽しめない作品なのかもしれません。ですが、事実に基づいた映画という面から見た場合、敢えて「真実に基づいた映像やストーリーを垂れ流しているだけ」という中立的な立場を取ることで、鑑賞する側にとって脚色や誇張のない”事実を伝える”ことができます。
これはまさに監督が伝えたかったメッセージでもあり、情報を多面的にみる大切さと真実を伝えるジャーナリズムの観点が上手く反映された中立的なノンフィクション映画となったのではないでしょうか。
監督本人として、この作品で伝えたかった真実を伝えるジャーナリズムを自らが具現化した映画といった点では、少し踏み込んだ映画の奥深い魅力が発見できるかもしれませんね。
また、この手法は今後のノンフィクション映画の新しい指標になってもおかしくない映画なのかもしれません。
【考察】狙ったかのような公開のタイミングはまさに奇跡
 (C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.もうひとつ、この映画の不思議な魅力は公開されたタイミングにあります。
これは、監督が意図していなかったため奇跡的なタイミングと言っても過言ではないのですが、アメリカでの『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』公開日は2018年7月13日、保守派である共和党のドナルド・トランプの大統領就任から約1年半後ということ。
トランプ政権誕生による国民の過激な右傾化が危ぶまれたアメリカに釘を刺すようなタイミングでの公開は、まさに過激な愛国主義に傾いたイラク戦争前のアメリカとの政治情勢と重ね合わせてしまいます。
映画の撮影開始と公開予定はトランプ政権誕生よりも前の2016年なので、本当にたまたまだったのでしょうが、過剰な愛国主義に傾いた時の恐ろしさや、個々が正しい情報の選択する重要性を考える良いタイミングになったのではないでしょうか。
また、もう一つのベストなタイミングは日本での公開日。日本での『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』は2019年3月29日ですが、同時期には『バイス』という『記者たち』と同じ時代背景の映画が公開されたのです。
この『バイス』という映画、当時の副大統領であるディック・チェイニー元副大統領の反省を描いた実話で、『バイス』が表舞台とするなら『記者たち』は裏舞台といった具合に、全く反対の角度からみた映画同士。
どちらも鑑賞することでより多面的にイラク戦争までの詳細を知ることができ、一層楽しめるかもしれませんね!